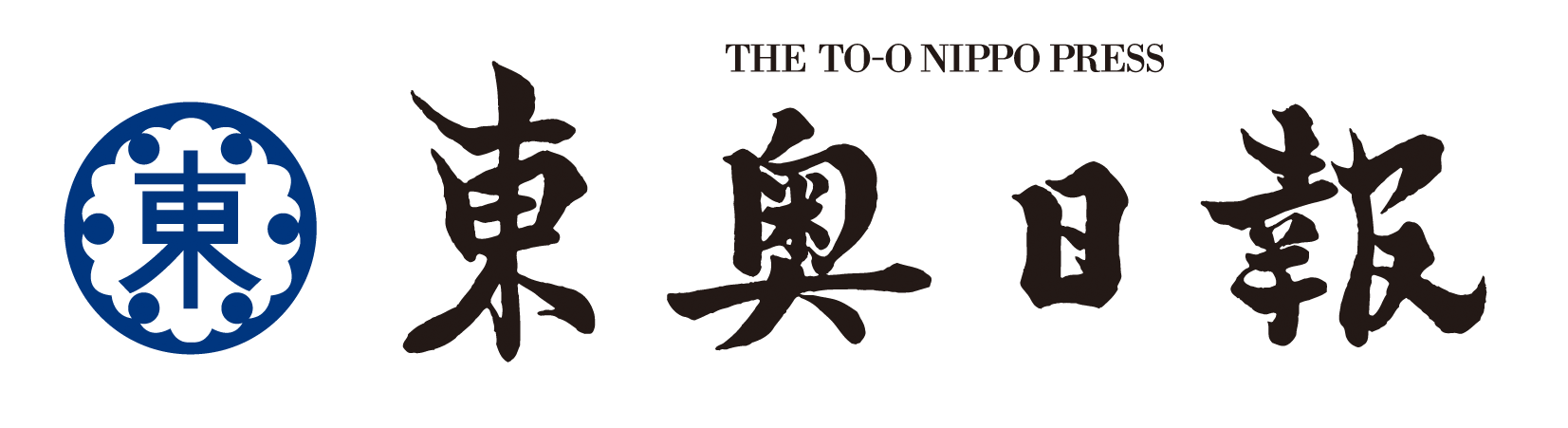第3話
序章
本土決戦に
備えた陣地
八戸要塞
(八戸市)




10月上旬、木々が色づき始めた八戸市の新井田川上流沿いで車を走らせた。
周辺には堅固なコンクリート製の構造物が点在する。
本土決戦に備えて造られた陣地「トーチカ」で、軍事施設が設置された蕪島などとともに「八戸要塞(ようさい)」と呼ばれていた。
戦時中、八戸周辺は米軍の上陸想定地とされ、「一億玉砕」が叫ばれる中で沖縄のような壮絶な地上戦に巻き込まれる可能性があった。
八戸要塞 太平洋戦争末期、本土決戦に備えて造られた陣地「トーチカ」や、蕪島に設置された軍事施設などの総称。戦況が悪化していた1944年8月、防衛総司令部は八戸付近、仙台付近、関東平地、浜松平地、南九州を米軍の上陸想定地と位置づけ、八戸市の是川、島守地区を重点に、同年10月から45年3月にかけてコンクリート製のトーチカを構築した。トーチカは現在、50基ほどが確認できる。建造には多くの住民や東北各県の学徒が動員された。だが、本土決戦に至らず終戦。実際に使われることはなかった。
敵弾から身を守る頑丈トーチカ
第1章 八戸市南郷・島守地区

本県の地域史に詳しい元中学校長の小泉敦さん(64)=五戸町=とともに、最初に八戸市南郷の島守地区のトーチカを訪ねたのは4月下旬だった。
島守地区は今も昔も自然に囲まれたのどかな農村集落だが、戦時中はひそかに本土決戦の準備が進められていた。トーチカには敵弾から身を隠す塹壕(ざんごう)もあり、弾薬庫や食料庫、避難所などとして造られた。
最寄りの道路からやぶをかき分け、山中を10分ほど歩くと、一つ目のトーチカが姿を現した。
標高160㍍ほどの高台にあり、はるか下に新井田川が流れる。小泉さんは「こんな場所までセメントを運んできたのか」と驚いた。
八戸要塞のコンクリートは質が良く、ひび割れもなく、現在使われているものと遜色ないように感じる。
このトーチカには高さ2㍍弱、幅1㍍弱の入り口があり、扉が設置されていた跡も。
階段を下りて、恐る恐る中に入ると、8畳弱ほどの広さだった。
地面には木片や土砂がちらばっているものの、実際には戦争で使用されなかったためか、壁や天井は戦後79年の月日を感じさせないほど真新しい。
見張り穴や煮炊きできるよう空気孔のようなものも存在する。
見張り穴
見張り穴
小泉さんは辺りを見渡しながら「厚くコンクリートが塗られている。かなり頑丈で丁寧な造りだ」と話した。

崖に立つ別のトーチカは高さ3㍍ほどで、中は3畳余りの広さと狭かった。



戦時中、島守地区にはトーチカ建設のため兵隊が集まり、民家や小学校に泊まったという。
地元で生まれ育った太田トモさん(87)は「終戦の時は国民学校の2年生。上級生はそりを引いて、冬に砂利を運ぶ作業をしていた。姉は新井田川からそりを引いて行った。この辺だけでなく、津軽や仙台出身の兵士が学校や家に泊まり、校庭でカボチャを植えていた記憶もある」と振り返った。
「学徒が資材を運搬し、陣地造りは兵士たちが昼夜3交代で行った。冬の食糧難の時代に大変な苦労だった。八戸要塞はモノとしてだけでなく、子どもたちが過酷な労働にかり出された場所として伝えることも大切」と小泉さん。
八戸市南郷歴史民俗資料館に八戸要塞に関する展示コーナーがあることを挙げ「経年劣化による事故防止を考えつつ、遺構を整備保存し、多くの児童生徒が戦争の学びを深める場になってくれれば」と語った。
「防空壕」山中にひっそりと
第2章 八戸市是川地区





八戸市是川地区で農業を営む差波紀一さん(80)の所有する山にもトーチカがある。
差波さんの自宅から、トーチカを建造する際に設けられた「兵隊道路」を通って15分ほど歩くと、手入れの行き届いた杉林の中に高さが3㍍ほど、幅は5㍍ほどのトーチカが姿を現した。
戦時中、付近には畑が広がっていたという。自身が生まれた時には工事をしていたが、「防空壕といわれていた。所有者ではあるけれど、詳しいことは分からない」と話す。
両親から、兵隊が集落で寝泊まりして、自宅でも風呂を沸かして入れたと聞いていた。ただ、「軍の機密事項で、この辺の人たちも何を造っているのか分からないまま、手伝わされていたのではないか」とみる。
近年は見学者がごみを放置する事態が発生し、トーチカがコウモリの飛来する場所でもあることから、現在は入り口が閉ざされている。中を見ることはできないが、8畳ぐらいの広さがあるという。
近くには「たこつぼ」と呼ばれる、人が1人入るのがやっとの広さの兵士の見張り用のトーチカが二つある。
以前は自衛隊員が研修で訪れたり、幹部が見学に来たりしていたという。差波さんは「もうこの辺では、戦時中のことを覚えている人はいない。戦争の記録として、トーチカの歴史を後世につないでいかなければならない」と語る。
厳寒期 総動員でセメント運び
終章 前八戸市博物館長の聞き取り
長年、住民に戦時中の聞き取りを行ってきた前八戸市博物館長の古里淳さん(64)=八戸市=の案内で新井田川周辺のトーチカ群を見た。
古里さんによると、トーチカは壁の厚さが60㌢~1㍍ほどのコンクリート製。階段を下りて中に入る造りとなっている。攻撃用と防御用があり、攻撃用は一般的に内部の空間が狭く、箱形で銃口を出す穴がある。防御用は広めで、天井はアーチ状となっている。
古里さんの母親はトーチカを造る際に、セメントを運んだ一人。1944年から45年にかけての冬は寒さが厳しく、県南地方でも雪が多かった。古里さんは「1、2月の寒い中、片道10㌔以上、セメント袋をそりに載せて3時間ほどかけて運んだと聞いた」と語る。
古里さんによると、小学校高学年の子どもから大人までが砂利運びなどを手伝い、八戸の女学生も動員され、湊地区のセメント工場から、重さ数十㌔もあるセメント袋をそりに載せて2人一組で運んだという。型枠作りは大工も携わった。
2002年8月10日の東奥日報朝刊には、当時八戸高等女学校(現八戸東高校)2年生だった女性の証言が掲載されている。
「本当に寒い冬だった。腰まで雪につかることもあった。でも、みんな頑張ろうってね、励まし合いながら運んだ」。防空頭巾をかぶった女学生がそりを並べて、列を作り、肩越しにロープを力いっぱいに引き、歯を食いしばって上り坂を上がっていった。
住民は当時、山中の自分の畑が突然、軍によって立ち入り禁止とされ、トーチカが造られていき、困ったという。
古里さんは「本土決戦の覚悟があり、作戦書も防衛省に残っている。(米軍が上陸するのは)砂浜があるところを想定していた。百石、三沢辺りかと思う」と指摘し「米軍がそこから新井田川に沿って少しずつ(内陸部に)攻め込むことを想定していたのではないか」とみる。
トーチカの多くは民有地にあり、解体の費用や労力が大きいため、戦後79年を経過してもなお、そのまま残っている。古里さんは「戦争を知る世代が次第に減る中で、トーチカは戦争を伝える遺構となった」と説明した。
東奥日報2002年8月10日朝刊
東奥日報2002年8月10日朝刊